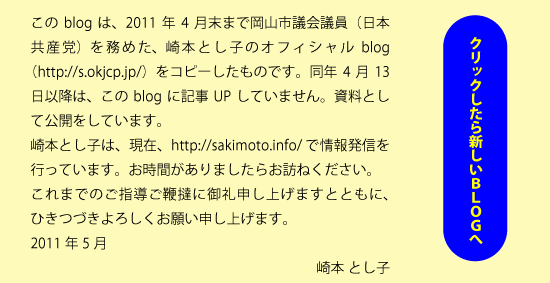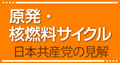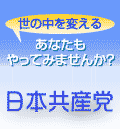日本でも「病院が患者を捨てる」時代?
「社会的入院」で病院にいる患者が半分いるとか。しかし、長期入院は診療報酬が低く、そういう患者をかかえると病院は倒産するしくみになっている。医療にお金をつかわない政策がつづけられている中で、今、医療現場は大変…。
だからといって、「退院に応じない患者」を公園に捨てるか?しかし、堺市の病院(私立)で実際におきた。この事例から、行政や政治家は何を考えなければならないのか…。
マイケル・ム―ア監督の「シッコ」の一場面を思いだし、アメリ力医療システムを追いかけている日本の現実に強い問題意識をもった。安心して病気を治せる日本の国でいたい!ありたい!
私の信条は「いのちは何より大切」である。いのちへのこだわりをもちつづけよう!!
国保料値下げと減免制度拡充などを要望
払える国保料に!の運動を執念をもって続けている。今日も、市社保協の皆さんと共に副市長へ要望書を届けた。
「高齢者の負担軽減に知恵をしぼりたい」と副市長は表明。
なんとしても実現したい。
8月、お金がないためかつて無保険状態だったKさんが遂に亡くなった。急にやせたKさんを見て、私は治療をすすめたが、病院へいくことを拒んだ。いったときは、手おくれの癌だった。払える保険料だったら、Kさんは国保証を手にできていたと思うと、胸が痛くなる。お金がないと病気の治療ができない制度は認められない。
Kさんの無念を胸に私は国保制度の改善にとりくんでいる。がんばるぞ!!
後期高齢者医療保険制度知りたいシリ―ズ?
保険料のことです。
75才以上の医療費の1割を加入者が負担するしくみです。したがって、当然総医療費が増えたら負担がふえる。だから、「健康寿命」を延ばそうと「健診」が義務付けられ、特定健診(シリ―ズ?)というわけです。保険料で「健診」をまかなわなくても、国民全員が対象なら、税金でやるべきと私は思います。
さて、話を戻すと、加入者1割分、後の9割を、国、県、市町村、そして国保や社会保険などの拠出金でまかないます。(おおざっぱにいうと)
国は1人当たり平均で6200円/月を示しました。岡山広域連合は6703円/月を案で示しています。平均より500円以上高い。なぜか…。総医療費が平均より高いから。病院がたくさんあって、かかりやすい体制が保険料の高い「原因」となる…!?だから、病院を倒産させて、残る所だけ残してかかりたくても病院にいけなくしよう―という政策が実施中。医師、看護師不足でやっていけなくなる病院、診療所が出ています。療養病床の廃止(38万→15万床)はその政策の中でおこっていることです。
保険料の集め方は、年金からの天引き。月15000円以上の人にこの「特別徴収」方式。全体の約90%の人はこの方法です。跡の10%は天引きでなく支払うことになります。広域連合は市町村にその仕事を委任。岡山市が支払い窓ロです。
払えなかったらどうなるか。
これまでは高齢者へは国保証を出さないことはなかったのですが、今回はちがいます。資格証明書が出せる法律になっているのです。
高齢者は誰でも病気をするから、国保法でも出さないことになっている資格証明書を高齡者医療制度では出巣ことになる―「お金のない者は国が捨てる」というひどい制度です。理念が之しいと思いませんか。私は許してはならないと思います。
アイデアいっぱいの操南ふれあいまつりと医療生協健康まつり
第8回目のはばたけ操南ふれあいまつりがあった。95才以上のお宝認定と
案山人コンテストなど楽しい!!アイデアマンが多い。そして、実行委員会のスタッフが多い。地域カありますね。
岡山医療生協は健康まつり。
多数の屋台が並んだ。三勲・旭東九条の会もフリ―マ―ケットを出店。多くの人と久しぶりの出会いがうれしかった。
午後は北公民館主催の女性議員と語る会。議員が10人出席した。(市議は7人)あっという間の2時間だった。
男女共同参画をすすめることは、民主主義を前進させることだ。悪しき慣習を変えて、先進諸国に恥ずかしくない仕組みをつくりたい。市議の女性議員比率は15%になった。40%をめざしたい。それぞれの議員のがんばっている様子は伝わったと思えた。公民館のこのような企画は大歓迎である。女性学発祥の地である北公民館はさすが…!と思う。
ソワ二工看護学校の載帽式へ
看護学校に入学して6?7ヵ月後、基礎実習を終えると載帽式がある。この間の学生の成長はめざましい。人としての成長をすると思う。他の学校のどれより、人として悩み、ぶつかり、そして失敗しつつそれを克服することで成長する。その根底にあるのは、「看護師になる」という目標だ。みんな輝いてた。おめでとうございます。
今日は、ご案内を板だ記載帽式に出席。私もキャッピングの日のことを思いおこした。3つのH…。
Head、Heart、Hand―知識と技術と心の大切さだ。科学的なものの見方、考え方を学んだのも看護学生の時だった。岡大看学時代なくして、今の私はない。私は、看護師である。
原点をしっかり見つめ、今しなければならないことを、1つ1つなしとげてゆきたい。